さて、伊勢に来たので城好きとしては津城を巡らねばお伊勢も片参りよっ。てことで、津城跡を巡ることにした。
妻は車で待機し、仕事をするとのこと。時刻は8時過ぎ。他の施設が営業前の時間帯、隙間時間、ロスとなりそうな時間でも巡れちゃうのは、城めぐりのメリットだ。

「城跡(一見何もない)」と7歳、3歳の「子連れ」は親和性が一見全くなさそう。城跡を眼前にしながら、泣く泣く諦める「城めぐりゃー(なんやんソレ?)」の方も多いのでは?
大丈夫です。工夫次第で城跡は子どもたちの大冒険の舞台へと変貌するのです!
津城跡の近辺には有料駐車場もあるが、西乃丸側にある津市役所の駐車場に停めて見学することができる。
津城跡は、現在「お城公園」として整備されている。大丈夫。子供公園大好き。

「よ~し!大冒険だぁ!城攻めじゃ~!!」
城めぐりゃーがいつも心の中で叫んでいることを、子どもたちの前で声に出せば喜んで城めぐりゃーの仲間入りをしてくれる(効果には個人差があります)。生き物好きなら、お堀の巨大なコイやカメで心をつかむのも良いだろう。

西之丸から城内へ攻め入ると、お手本のように鍵型(桝形)となっている。子供たちはダッシュで速度を落とさず見事に曲がり、その先の二階門跡の石段をよじ登り、あっという間に西之丸の虎口を制圧した。
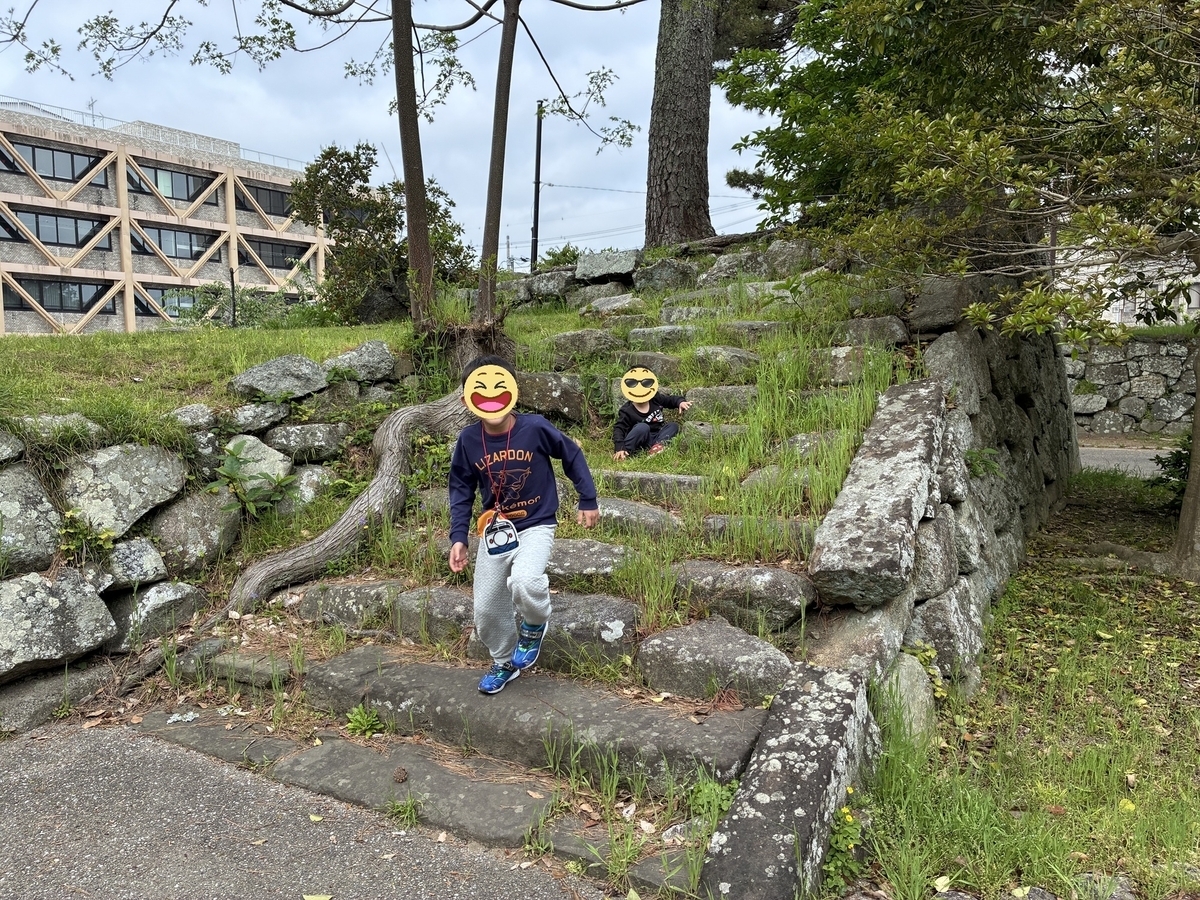
西之丸は庭園になっている。ここには、文政3(1820)年に津第十代藩主・藤堂高兌(とうどうたかさわ)によって開設された藩校・有造館の講堂の正門であった「入徳門」が移築・現存している。

入徳門の名は、「大学は諸学徳に入る門なり」という言葉から来ており、厳格な作法をもって入門していたという。明治になり廃校となった後、小学校、師範学校、中学校、女学校、幼稚園、図書館と様々な生徒や学業の徒を見届ける門の役割を果たし、昭和62(1987)年に保存修理のための解体復原工事を経て現在に至る。
戦災も奇跡的に免れたというこの入徳門ほど学業の正門としての役割を果た続けた門は数少ない稀有な存在なのではなかろうか。ウチのちびたちも学問に励んでほしいと願い「ほれ、くぐれ!」と促すも「やーだよ」とかわされてしまい彼らはどんどん進んでいく。

西之丸から土橋を渡り本丸へ向かう。今や埋められており本来の曲輪の輪郭がよくわからなくなっているが、外から見ると土橋の雰囲気は解る。
下の写真で言うと、右(手前)が西之丸で、凹んだ通路のように見えるのが土橋、写真左側(奥)に本丸戌亥櫓跡石垣が見える。

土橋から戌亥櫓跡を眺め「ここにお城があったんだぜ」と解説する。子供用に言い換えているが、ここで言う「お城」とは戌亥三重櫓のことだ。

雲が少し晴れてきて、その光の粒の先に丑寅櫓が見えてきた。「あ!お城~?」と3歳の次男が見つけ、ふたりしてまた走り出す。

彼らは瞬く間に丑寅櫓跡を制圧するも、その櫓台の高さに私の方がびっくりして子供たちが落ちないか心配だった。

真剣な話、落ちたら多分死ぬので、こういう場面では本当に気を付けた方が良い。

子供は死への実感が少なく、またどの程度で死ぬかという感覚が未熟なので、危なかったら近寄せないのが一番だ。

「もういいからお城に行こう」
割と本格的に怖くなったので、子どもたちを丑寅櫓へと誘う。

「ここから、鉄砲とか弓矢で、外にいる敵を狙うんだぜ」
「どうしてぇ?」

「城って、戦争のためにあるんだよ」
「なんでぇ?」
「人って、割と食べ物がなくなると戦争するみたいだよ」
「どうしてぇ?」

どうしてだろう。食べ物がないなら、わけあえば良いのに。なんだか禅問答みたいで考え込んでしまった。人はどうしても戦争したいのだろう。
模擬の丑寅櫓から一旦本丸の中央方面へ戻り、藤堂高虎公像と対面する。
藤堂高虎は戦国時代の武将で、到底一言で表せる人ではないが、できるだけ簡潔に説明する。

まず主君選びの名人である。7度主君を変えたことで有名だが、大まかに浅井→豊臣→徳川と主君を変え、その都度主君は繁栄した。次に築城の名人でこの時代の第一人者である。この人が携わった城は、この津城はもちろん、赤木、宇和島、今治、大洲、伊賀上野など、どれも日本100名城、続日本100名城に選定されている。領国経営にも長けていたと言われ、主君を何度も乗り換えたにもかかわらず裏切り者の暗さがない。徳のある人だったようだ。

本丸には天守台が残っていて、高虎以前に織田信包が5層の望楼型天守を建てていたが関ヶ原の役の余波で焼失、その後3層の天守を再建したが江戸初期にこれも焼失し、以後は戌亥櫓、丑寅櫓が天守の代用となった。

本丸の南側に埋門がありここから外へ出た。この先には高虎得意の「犬走」という石垣下から水堀までの間に、狭い幅の通路があり、丑寅櫓手前の太鼓櫓まで続いていたという。緊急脱出通路とでも言えようか。

埋門から外へ出ると、お城公園という遊具のある広場になっているが、天守台や小天守台の雄大な石垣を眺められるスポットでもある。

子供たちには遊具で遊んでもらい、そのうちに公園の奥の石垣たちを堪能した。

公園から見える石垣には、積み増した石垣の切れ目が見て取れる。上の写真でも見れるが、相当拡大しないとわからない。時代の変わり目が分かる石垣はぜひ間近に撮っておきたかったが、子連れの弱みの一つだろう(ちなみに2009年に一度来ているが、この時も歴史好きの親父と来ているにもかかわらず気付いていない)。

まだ遊びたがる子どもたちを説得し、堀跡づたいに東多門櫓が載っていたであろう石垣を眺めつつ、丑寅櫓へ戻る。

丑寅櫓は、昭和33(1958)年に、東鉄門に隣接した多門櫓の跡地に建てられた、観光用の模擬櫓である。

史実との違いは多々あるが、元の丑寅櫓は装飾性を排除していたが、現丑寅櫓は観光用なので破風があるなど、要するにカッコよく造られている。
うん、確かにかっこいいぞ!

とかく、こういった模擬櫓、模擬天守は批判されがちだけど、初代の5層天守は23年、二代目は長く見積もっても50年で焼失している。昭和に建造された3代目はすでに65年を超えて、津城下を見守っている。

平和な時代にあえて作り、都市のシンボルとして、また市民の憩いの場として存続している。これはむしろ、歴史的快挙と言えるのではないか。平和や、この地域の象徴としての丑寅櫓を思う時、私は強く愛おしさを感じるのだ。

江戸期、津の城下は伊勢参りの宿場町として大いに栄え、こう謳われた。
「伊勢は津で持つ 津は伊勢で持つ」
伊勢音頭の一節である。その時代が去った後、自ら立ち、不器用ながらに「お城」を建てた津市。

歴代の殿様だって、「そうじゃ、このように格好の良い城を建てたかったんだ」と、幕藩体制で思うままに行かなかった当時の築城を自嘲しながら讃えてくれるのではないか。

「あ、おっきな鳥さんいるよ!」
「亀さん3匹みつけたらかえろー」

まとめとしてはちょっと微妙な気もするけど、外来種さえも受容しつつ、お堀は今でも水を湛えているのだ。ちなみに、犬走も模擬である。
つづく👇
ブックマーク&ブログランキング 応援してね!
| 🏯🚼 津城跡 ~メモ~ 🏯👶 | ||
|---|---|---|
| 私の所要時間 | 53分 | |
| 住所 | 三重県津市丸之内33-5 | |
| 登城時間 | いつでも | |
| 休業日 | なし | |
| 駐車場 | あり。無料(津市役所の駐車場)。近隣に有料もあり。 | |
| アクセス | 近鉄名古屋線津新町駅から約徒歩13分。津駅からバスあり。 | |
| ホームページ | 津城(お城公園) - 津の時間。(津市観光協会) | |
| 👑 津城跡の称号 🔱 | ||
| 続日本100名城 | (152) 津城 | |